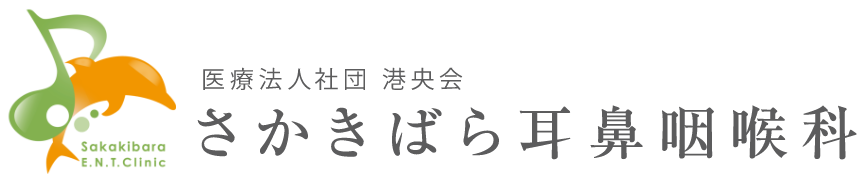めまいが繰り返し、耳鳴りや難聴が気になる方へ
「その症状はメニエール病かもしれません。当院では正確な診断と再発予防に力を入れています。」
メニエール病は、突発的に強いめまいを繰り返す中で、耳が詰まった感じ、耳鳴りや難聴を感じる病気です。症状が続くと日常生活への影響が大きくなることもあり、適切な診断と治療が重要です。ここでは、病気の特徴・原因・診断・治療・生活の工夫まで、患者さんにとって役立つ情報をわかりやすく解説します。
メニエール病とは
内耳(蝸牛・前庭)の機能障害で起きるめまいの病気です。内耳の液体のバランスが崩れる「内リンパ水腫」が原因と考えられており、繰り返す回転性めまいが数十分〜数時間続くことが多いです。めまいの前後に耳鳴りや耳が詰まった感じ(耳閉感)、一時的な難聴が見られ、症状は日を追って変動します。成人を中心に発症しますが、性別差は大きくなく、様々な年齢層で発生します。ストレスや睡眠不足、塩分の取りすぎなど日常生活の刺激が発作を招くことがあります。
主な症状と特徴
「こんな症状が続いていませんか?」
- 激しい回転性めまいが数十分〜数時間続く
- めまいの前後に耳鳴りや耳の詰まった感覚がある
- 難聴があり、症状が治まっても聴力が回復と変動を繰り返す
- ストレス・過労・気圧変化で悪化することがある
- 吐き気や嘔吐を伴うことがある
原因とメカニズム
内耳の液体のバランスが崩れ、内リンパ水腫が起きると、蝸牛・前庭の圧力が上がり、聴覚・平衡感覚に影響します。自律神経系やホルモンバランスの乱れも、ストレスや睡眠不足が引き金となり内耳の機能を乱しやすくします。日常生活においては、塩分の摂りすぎや不規則な生活、過度のストレスなどが発作を招くと考えられています。
診断方法
メニエール病の診断は、聴力検査と平衡機能の検査を組み合わせて行います。めまいの発作の性質(回転性か、長さ、頻度)や耳鳴り・耳の圧迫感の有無を詳しく伺い、他の病気を排除します。必要に応じて画像検査を補助的に用い、長期的な経過観察も重要です。診断は専門医の総合判断で決まり、治療方針は検査結果と症状を踏まえて一緒に決めていきます。
治療法
メニエール病の治療は、まず生活指導が基本です。塩分とカフェインを控え、適度なストレス対策を取り、十分な睡眠を心掛けます。薬物療法では、利尿剤や循環改善薬、ビタミン剤などを症状に合わせて調整します。めまい再発を減らす生活習慣指導と並行して、必要に応じてリハビリ(前庭リハビリ)やカウンセリングを行い、心身の安定を図ります。専門医が経過を見ながら適切な方針を一緒に決定します。
再発予防・生活上のアドバイス
ストレスを減らし、規則正しい睡眠リズムを心がけましょう。食事は低塩を意識し、水分は適量を維持。カフェイン・アルコールは控えめにします。天候や気圧の変化には無理をせず、急な動きを避けて安静を取ることが大切です。運動は無理のない範囲で続け、定期的に医師の経過観察を受けてください。
他のめまい疾患との違い
| 疾患 | 主な特徴 | 発作の 持続時間 |
発作の誘因 | 発作の 頻度・部位 |
治療の考え方 |
|---|---|---|---|---|---|
| メニエール病 | 回転性めまい+耳鳴り・難聴・耳の詰まり感を伴うことが多い | 数十分〜数時間が典型 | ストレス・睡眠不足・天候・塩分過多など日常要因 | 長期的に繰り返すことが多い。片耳から始まり、時間をかけて左右に移ることも | 内耳のむくみを抑える薬や生活習慣の工夫、発作の予防が中心。急性期は安静と対症療法 |
| BPPV(良性発作性頭位めまい症) | 特定の頭の動きで短時間の回転性めまいが起こる | 数秒〜数十秒程度 | 頭の急な動き、頭を特定方向へ動かしたとき | 短時間で再発しやすいが、発作は回転感が主 | 耳石を元の位置に戻す「エプリー法」などの頭位療法が有効なことが多い |
| 前庭神経炎 | 突然の長時間続くめまい、吐き気・嘔吐を伴うことが多い | 数日以上に及ぶことが多い | ウイルス性炎症などが関与とされるが特定は難しい | 発症頻度は比較的少なく、片側性が多い | 薬物療法とリハビリ(前庭リハビリテーション)を組み合わせて回復を目指す |
受診の目安
「めまいが繰り返す」「耳鳴りが続く」場合は早めの受診をおすすめします。
特に以下の場合は急を要することがあります。
- 強いめまいが突然起こり、嘔吐を伴う
- 吐き気が強く、日常生活に支障が出る
- 難聴が一時的ではなく継続する
まとめ
メニエール病は、早期に適切な治療を受けることでコントロールが可能です。めまいでお困りの方は、まず一度ご相談ください。
港北区・妙蓮寺駅近くのさかきばら耳鼻咽喉科では、正確な診断と再発予防を目指し、生活指導と薬物療法を組み合わせた総合的な治療をご提案します。必要に応じて前庭リハビリやカウンセリングも併用し、患者さんごとに最適な診療計画を一緒に考えます。